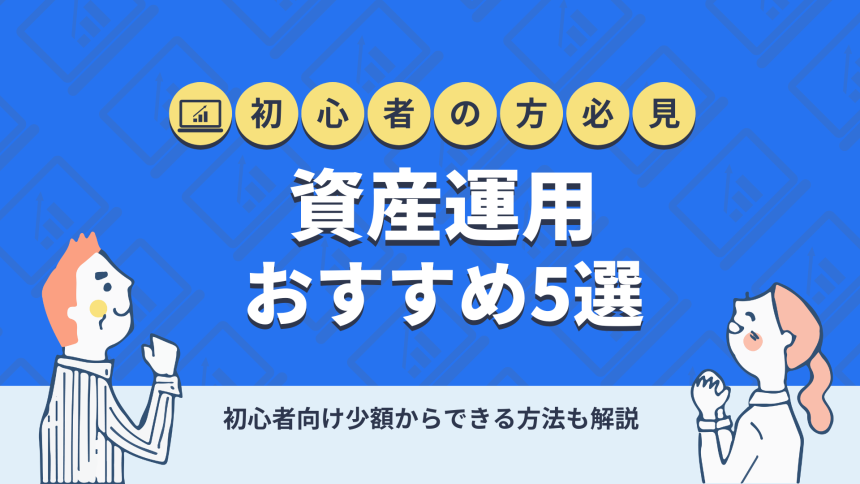
資産運用おすすめ5選!初心者向けの少額投資の方法・注意点も解説
マネースタート(以下、当メディア)はユーザーがより有益な意思決定を行えるように独自で定めた「コンテンツ制作・編集ポリシー」や「広告掲載ポリシー」に基づき制作に努めています。紹介する商品の一部または全部に広告が含まれておりますが、公平性を欠いた特定商品の過大評価や貶める表現などをポリシーで禁止事項として取り決めており、各商品の評価や情報の正確さに一切影響する事はありません。また、各商品に関して「評価方針・比較基準」を作り込み、客観的且つ中立的な観点より情報提供することを第一としています。訪問ユーザ様から取得しているデータ(アクセスや広告IDなど)に関しては「外部送信規律に関する表記」をご覧ください。
【数字で見る本記事の信頼性】
・金融庁「金融商品取引業者一覧」の1969社から抜粋
・各案件を当メディア独自の5項目基準で採点化。
・ネット証券に関する独自アンケートにより500名以上の取引者から回答取得。
「資産運用を始めてみたいけれど、何から始めたらいいかわからない」という方は多いのではないでしょうか?特に初心者の方は、なるべく低リスクかつ少額から資産運用を始めたいですよね。
そこで、この記事では初心者にもおすすめな資産運用を5つ紹介します。中長期的にコツコツ資産運用すれば、100万円や1,000万円など大きな利益に近づくことができるかもしれません。

2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。監修者の詳細はこちら
・MDRT入賞9回
・CFP
・IFA(証券外務員1種)

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。監修者の詳細はこちら
・MDRT入賞7回
・CFP
・IFA(証券外務員1種)

「あなたらしい暮らしのスタートライン」マネースタートは、生活に必要なお金に関する知識や情報を発信するメディア。お金を通じて、一人ひとりのニーズに合わせたライフプランを考えるきっかけをお届けします。編集部ではユーザにより役立つ情報をお届けするためにFP2級を勉強中。制作ポリシーはこちら
管理元 / ブロードマインド株式会社

当メディアでは「金融商品取引法」に則り、金融庁の金融商品取引業者登録一覧に記載ある事業者または、日本証券業協会の協会員として登録されている事業者のみを紹介しています。また、当メディアに掲載している評価点数やガントチャートグラフ、ランキングは、各証券口座の公式サイトの情報や公的機関の情報をもとに制作しています。詳しくは「ネット証券口座の比較基準・ランキング根拠(PDF)」をご覧ください。本記事の内容は、資産運用のリターン・リスクについていかなる確約をするものでもありません。資産運用は自己の責任において行っていただきますようお願いいたします。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
金融商品取引法における広告等規制について
広告等に関するガイドライン
>>当サイトおすすめネット証券の概要まとめはこちら(PDF)
目次
資産運用とは

資産運用とは自分の手持ちのお金を使って、資金を増やしていくことです。
資産運用にあたっては「リターン」と「リスク」について、慎重に考える必要があります。
| リターン | 資産運用によって得られる利益のこと。 |
|---|---|
| リスク | リターンの振れ幅のこと。 |
資産運用の種類とは
資産運用においてリスクとリターンはそれぞれ3段階(ロー・ミドル・ハイ)に分けられます。
主な資産運用の種類は、以下のとおりです。
| ローリスク ローリターン |
|
|---|---|
| ミドルリスク ミドルリターン |
|
| ハイリスク ハイリターン |
|

初心者におすすめの資産運用5選

資産運用は多くの種類があり、何から始めたらいいかわからないという方も多いと思いでしょう。
ここからは初心者の方でも安心して利用できる「ミドルリスク・ミドルリターン」の資産運用を中心にご紹介します。
1投資信託
初心者におすすめな資産運用は「投資信託」です。
投資信託では、投資家から集めたお金を運用のプロである「ファンドマネージャー」が投資のために運用します。

投資家たちは、ファンドマネージャーが利益を得た場合には配当金を受け取ることができますが、価格が変動する金融商品を扱っているため自分が投資した元本保証はありません。
投資信託は、主に以下の4つの理由から初心者におすすめです。
投資信託がおすすめの理由
- リスクの分散が可能
- 少額の資金からOK
- 運用のプロに任せることが可能
- 選択肢が豊富である
理由① リスクの分散が可能
先ほども説明した通り、投資ではリスクを分散させることが大切です。投資信託では1つの投資先ではなく、
- 株
- 債権
- 不動産
- 資産
などの複数の投資先を運用に組み入れているため、リスクを分散することができます。
また、商品選びや銘柄選びも全てファンドマネージャーが行ってくれるので、初心者の方でも安心です。
理由② 少額の資金から可能

投資をするには、ある程度のお金を準備する必要があります。
しかし投資信託では、投資家から集めたお金をまとめて運用してくれるため、1人の投資額が少なくても複数の投資先へ投資することが可能です。
理由③ 選択肢が豊富にある
投資信託は大きく分けると、
- 株式投資信託
- 公社債投資信託
の2つに分けることができます。「株式投資信託」では株式を組み入れた運用がされている一方、「公社債投資信託」は株式が組み込まれていない運用です。
他にも分類方法がたくさんあり、
- 購入可能期間
- 投資する地域
- 投資対象
によっても細かく分類することが可能。選択肢が多いので、自分の目的にあった投資信託を選ぶことができます。
理由④ プロに運用を任せることができる

投資信託は、ファンドマネージャーが運用のプロとして投資先選びから取引までを全て代わりに行ってくれます。
そのため「投資や資産運用に関する知識はないけれど興味がある」という初心者の方にはぴったりです。

投資信託のリスク
投資信託にはメリットがあるぶん、以下のようなリスクもあります。
- 元本保証がない
- コストがかかる傾向にある]
元本保証がない

投資信託は価格が変動する商品を投資対象としているため、元本より値下がりしてしまったり、投資先の倒産などのリスクが考えられます。そのため、元本保証がなく損失を被る場合があることも覚えておきましょう。
また、海外と取引している投資信託は「為替変動リスク」や「カントリーリスク」も考えられます。
コストがかかる傾向にある
投資信託は、ファンドマネージャーに投資を依頼するため手数料がかかります。
主な手数料は、以下のとおりです。
| 購入時 手数料 | 購入時や換金時に販売会社に支払う費用。 申し込んだ額の数%を費用として支払う。購入時手数料がないこともある。 |
|---|---|
| 運用管理 費用 | 投資信託を支払う間、保有額に応じて支払う必要のある費用。 年率何%を払うか決まっているため日割計算し日々支払っている。信託財産から差し引かれる。 |
| 監査報酬 | 投資信託の監査にかかる費用。 投資信託は決算ごとに監査法人からの監査が義務付けられている。信託財産から差し引かれる。 |
| 売買委託 手数料 | 投資信託が株式などを売買する際にかかる費用。 運用によりかかる費用のため、事前にいくらかかるかはわからない。発生する度に、信託財産から差し引かれる。 |
| 信託財産 保有額 | 投資信託を購入・解約する時に支払う費用。 運用資産に組み込まれる。投資信託によって差し引かれるものと差し引かれないものがある。 |

2REIT(不動産投資信託)

初心者の方には不動産に特化した投資信託である「REIT(リート)」もおすすめです。しかし、不動産投資に興味があっても「初期コストが高そう」と思い切って始められない方もいらっしゃるでしょう。
REITでは、複数の不動産に少しずつ投資できるうえ、不動産の選定などは知識豊富なプロが行ってくれるため初心者の方にもおすすめです。
REITの主なメリットは、以下のとおりです。
- 高い分配金を得ることが可能
- プロに任せることができる
- 少ない金額からOK
- 分散投資が可能
高い分配金を得ることが可能

REITでは投資法人という形態をとっているため、高い分配金が特徴になっています。
投資法人は利益の90%以上を分配することで法人税を払う必要がなくなるため、結果として分配金が株式などに比べて高くなるのです。
不動産は「いい物件」を選ぶことができれば長期で安定した収入が期待できるので、高水準な配当金を望めることは大きなメリットだといえます。
プロに任せることができる
不動産投資は、安定しており利回りが高水準なことがメリットですが、不動産の選定や売買にはやはり専門的な知識が必要です。
REITも投資信託と同様に、運用のプロに不動産の選定から任せることができるため、複雑な手続きはプロに任せることができます。
少ない金額からOK

REITでも投資信託と同様に、少ない金額から始めることができます。
実際に、自分だけで不動産投資をしようと思うと、それなりのまとまったお金が必要です。
なので初心者には少しハードルが高く感じられますが、REITでは数万円単位から投資が可能なため始めやすいことが特徴です。
分散投資が可能
REITは複数の不動産に小額ずつ投資することができるため、リスクを分散させることができます。
不動産は投資額が大きいため、複数保有し分散投資を行うことは難しいですがREITでは可能です。
そのため、投資先の1つの不動産で空室が発生してしまったり、下落してしまったとしても他の不動産でリスクを抑えることができます。
また、不動産が複数あるだけでなく広範囲の地域で様々な用途の不動産に投資しているためリスクを分散させやすいです。
REIT(不動産投資信託)のリスク
REIT(リート)にはどのようなリスクがあるのでしょうか?主に以下の5つのリスクが考えられます。
- 実物が所有できない
- 自然災害のリスク
- 投資法人の倒産リスク
実物の不動産を所有できない

REITにいくら投資しても、分散投資されてしまうため実物の不動産を所有することはできません。
実物不動産投資をした場合には、自分で所有することが可能なため状況に応じてはそこに住むこともできますがREITでは不可能です。
投資法人の倒産リスク
投資法人も、一般の企業と同様に倒産してしまう可能性があります。
倒産してしまった場合には、不動産を売却し投資家へ投資金が返ってくることもありますが全額返ってくる保証はありません。
自然災害のリスク
REITは不動産への投資のため、自然災害などにより不動産の価値が下がってしまうと分配金が減少してしまうリスクがあります。
また、相場の変動も激しく金利の影響も受けることがあるでしょう。
3株式投資

株式投資は、株式会社が資金を調達するために行われる投資方法です。
株を購入した人は、株主と呼ばれ配当金の受け取りや株主優待を受けることができるようになります。
株式投資が初心者におすすめな主な理由は、以下のとおりです。
- 少ない資金でも投資が可能&優待を期待できる
- 多くの投資先から選ぶことができる
少ない資金でも投資が可能&優待を期待できる
株式投資には、多額の資金がないと始めることができないと考えている方も多いかもしれません。
しかし、実際には少ない資金でも投資をすることが可能なのです。中には、投資をするだけでなく数万円で株主優待を受けることができる企業もあります。

多くの投資先から選ぶことができる
株式投資では、投資する企業をひとつずつ自分で選ぶことができます。そのため、サービスや商品を見極めて投資するかどうかを検討することが可能なのです。
一見「初心者には難しそう…」と感じるかもしれませんが、はじめは自分が好きな企業や株主優待目当てで株を購入してみましょう。
株式投資のリスク
株式投資の主なリスクは、以下のとおりです。
- 価格変動商品のため値下がりリスクがある
- 為替変動リスク・カントリーリスク(外国株式の場合)
- 投資先が倒産する可能性がある
また、外国の株式を購入した場合には為替によるリスクやカントリーリスクも関わってくるため、注意が必要です。
価格変動商品のため値下がりリスクがある
株式投資では、買った株が値下がりしてしまうと損失が発生してしまいます。いわゆる「元本割れ」のリスクです。
株価は常に変動しているため、買った株が値下がりし購入時より安い値段でしか売ることができないといったリスクが発生してしまうため注意が必要です。
為替変動リスク・カントリーリスク(外国株式の場合)
外国株式を購入した場合、投資信託と同様に為替変動リスクやカントリーリスクが考えられます。
これらのリスクに対応するためにも、1つの株式を一度に買うのではなくタイミングを分けたり複数の会社の株式を購入することが重要です。
投資先が倒産する可能性がある
株式投資では、投資した企業が倒産してしまうと最悪の場合株式の価値がゼロになってしまいます。
株式の価値がゼロになってしまうと、その企業に投資したお金は返ってこなくなってしまうため分散投資を心がけることが重要です。
4債券投資

最後にご紹介する資産運用は、債券投資です。債券とは、国や企業などが資金を集めるために発行する有価証券のことを指します。
特に国が発行している国債の場合には、国が潰れない限り元本が保証されるため「元本より減らしたくない」という方にはおすすめです。
利払日に利息が支払われ、投資家に元本が戻ってくる償還日には、額面金額が払い戻されます。
債権は有価証券であるため償還日を待たなくても売却することが可能ですが、その場合元本割れのリスクがあることも忘れてはいけません。
債券投資が初心者におすすめの主な理由は以下のとおりです。
- 預金よりも高金利である
- 手軽&低リスク
- 利益の計算が簡単
- 売却益を狙える
預金よりも高金利

債券投資は、通常の銀行よりも金利が高く設定されています。
一方で債券投資では、個人向け国債の下限金利が0.05%と、一般的な銀行の金利よりも高い金利が設定されています。
銀行預金よりリスクはあるものの大きな利益を得ることが可能であるといえます。
手軽&低リスク
債券投資は株式投資に比べ、専門知識がなくても手軽に投資することができるというメリットがあります。
その一方で債券投資では、投資先を決定してしまえば保有しているだけで利益を得ることを望めます。
また、債券投資は発行時に定められた利息が支払われることに加え、発行体が経営悪化や倒産をしない限りは元本が戻ってくるためリスクがそこまで高くはないと考えられます。
株式と比べて安定した値動きが特徴なため、発行体の安全を見極めることが重要になってきます。
利益の計算が簡単

債券投資では、簡単に利益の計算をすることができます。
株式投資では、値上がりのタイミングなどを完全に予想することは不可能です。しかし、債券投資では「償還期間」と「利率」が決まっているので、自分が得ることのできる利益の計算を比較的簡単に行うことができます。
そのため、特に固定金利の債券であれば初心者の方であっても今後の計画を立てやすいです。
売却益を狙える
債券では、売却益を狙うことも可能です。債券は償還日まで保有し額面価格を受け取るだけでなく、償還日前に売買することも可能です。
ただ、この時の注意として市場の状況によっては元本割れをする可能性もあることを覚えておくことが重要です。
初心者の方には少し難易度が高いかもしれませんが、慣れて余裕ができたら挑戦してみてもいいでしょう。
債券投資のリスク
債券投資にも、もちろんリスクは存在します。債券投資で考えられる主なリスクは、以下のとおりです。
- 信用リスク
- 価格変動リスク
信用リスク

国が発行体である国債では考えづらいですが、企業が発行体である社債では、購入前に信用リスクについて考える必要があるでしょう。
確かに、債券投資は手軽に利用できますが、債券選びは手を抜かずにしっかりと調べましょう。
価格変動リスク
株式に比べて安定しているものの、市場で取引できる債券も価格が変動しています。
また外国の債券を購入している場合には、為替レートが変わっていることによるリスクも考えられます。
5iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことを指します。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。
iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。
つまり、自分で老後の準備のために作る年金制度のことです。老後の生活をゆとりのあるものにするためには、やはり多くの資金が必要になります。
公的年金だけでは、全てを賄うことは難しいのです。また、iDeCoを使うと節税対策にもなるため今ますます注目されています。
iDeCoが初心者におすすめな主な理由は以下のとおりです。
- 多くの人がiDeCoに加入することが可能
- 節税対策になる
多くの人がiDeCoに加入することが可能
iDeCoへの加入条件は、以下のとおりです。
- 原則20歳以上60歳未満
- 公的年金に加入している
iDeCoは、公的年金だけでは将来が不安な人のために誕生したものです。そのため、公的年金に加入していない人はiDeCoに加入することができなくなっています。
また、60歳未満であればほとんどの職種の人が加入することが可能です。雇用形態にも制限がないため、老後の備えとして多くの人が活用しています。
節税対策になる
iDeCoでは、以下の3つの段階で節税優遇を受けることができます。
- 積立時
- 運用時
- 受取時
積立時には、所得税と住民税が軽減されます。

また、運用時には運用利益が非課税になるため投資信託で運用する場合にかかる税金(20.315%)を節税することができます。
さらに、受取時には60歳以降だとどのような受け取り方法を選択しても税金がかからないため、節税面に関してはこれもiDeCoの大きなメリットといえるでしょう。
iDeCoのリスク

iDeCoでは、以下の点が主なリスクとして考えられます。
- 原則60歳まで引き出せない
- 選ぶ運用商品によって元本割れしてしまう可能性がある
- 手数料がかかる
iDeCoは、自分で運用商品を指定する必要があるため選ぶものによっては損失になってしまうことがあります。
リスクを避けた運用商品を選ぶことも可能ですが、手数料がかかってしまうことも忘れてはいけません。
ここからは、iDeCoを利用する上で考えられるリスクについて説明します。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoは年金の一種であるため、積み立てた資金は原則60歳になるまで引き出すことができません。
そのため、儲かってもすぐに引き出すことができない点には注意が必要です。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。
このため、60歳にならないと原則として年金資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません。
ただ、すぐに現金化できないということはメリットとも考えられます。強制的に長期投資ができる上に、途中で投げ出してしまう心配もありません。

選ぶ運用商品によって元本割れしてしまう可能性がある

iDeCoでは、どの運用商品に投資をするかの決定権は全て加入者が持っており、運用のリスクは加入者であるみなさんが負うことになるため注意が必要です。
しかし、iDeCoで扱われている運用商品は分散投資されているものが多いためリスクも抑えられているものが多いです。
iDeCoには、定期預金や保険のみを運用する「元本確保型商品」が用意されているため諦める必要はありません。
手数料がかかる
iDeCoでは、積み立てする際にかかる手数料を全て自己負担しなければなりません。
iDeCoにかかる手数料は主に以下のとおりです。
| 加入時・移換時 手数料 | 企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金への移換時に発生する手数料のこと。 初回のみ税込2,829円かかる。 |
|---|---|
| 加入者 手数料 | 掛け金納付の際に毎回かかる手数料のこと。 納付の都度税込105円かかる。 |
| 還付 手数料 | 加入者が国民年金を納めなかった月に発生する手数料のこと。 iDeCoからの還付金から税込1,048円差し引かれる。 |
このように並べると多くの手数料がかかるように感じる方も多いと思います。
しかし、実際にはiDeCoの大きなメリットである掛金の全額所得控除による節税効果を考えるとそこまで多くの損失は発生しないと考えて基本的に問題はありません。
資産運用が初めてで不安な方は全自動の資産運用サービスがおすすめ
資産運用をこれまでしたことがない方は、全自動の資産運用サービスを活用することをおすすめします。
今回は、誰でも簡単に利用できる資産運用サービス、「WealthNavi(ウェルスナビ)」についてご紹介します。
まずは、ウェルスナビの基本情報を見ていきましょう。

| 最低投資額 | 10万円 |
|---|---|
| 手数料 | 年率1.1% |
| NISAの自動運用 | 対応 |
ウェルスナビを利用するメリット
ウェルスナビは他の資産運用サービスと比べてどのような点が優れているのでしょうか。大きなメリットとして、一人ひとりに適した運用プランを提供してくれることでしょう。

その他にもウェルスナビのメリットは以下のようなものがあります。
- 長期投資に適している
- スマホから簡単に投資できる
- おまかせNISAで利益を非課税にできる
- 多くの種類の銘柄に投資できる
- ロボアドバイザーにより自動で資産運用できる
- 提携先のマイルやポイントも貯まる
ウェルスナビは、他の資産運用サービスと比べても手数料の安さやNISA対応といった使いやすさが特徴です。
また、預かり資産7,500億円を突破した実績もあり、これから長期投資を始めたい方におすすめの資産運用サービスといえるでしょう。
ウェルスナビの利用がおすすめの人
ウェルスナビにはさまざまなメリットがあり、使う人によっては長期投資を有意義なものにしてくれるサービスです。
次の項目に当てはまる内容がある方は、ウェルスナビの利用をおすすめします。
- スマホアプリだけで入金や取引がしたい人
- NISA口座でウェルスナビを使いたい人
- 投資に関する知識が少ない人
- 放置状態でも資産運用をしたい人
ウェルスナビは唯一NISA口座にてロボアドバイザーが使える資産運用サービスで、約50カ国11,000銘柄に投資することが可能です。
また、日々の生活が忙しくなかなか投資に取り組めない人や、出先でも投資や収支確認をしたい人など、多くの人のニーズに応える機能がそろっています。

資産運用の選び方

1投資に回すことができる資産額で選ぶ
投資に回すことができる資産額によって、運用できる金融資産は異なります。例えば、個別銘柄株式への投資などの場合は、最低100株単位での購入が一般的で、最低でも数10万円程度の元本が必要になります。
反対に、投資信託やETFへの投資であれば、積立投資の制度を利用して毎月数100円から資産運用を行うことができます。大きな資産を作るまでには時間がかかりますが、少額の資産でも資産運用を始めてみたいという人にはピッタリです。
証拠金として資産を預けることで、少額の資産しかなくても大きな資金を動かすことができる「レバレッジ」という投資方法があります。

2リスクやリターンの大きさで選ぶ

資産運用は、資金を投資する金融商品によってリスクやリターンが大きく異なります。少額の投資でも、比較的大きなリターンを得られる可能性がある金融商品の中には、仮想通貨やFXなどがあるでしょう。
一方で、大きなリターンを得られる可能性がある金融商品は、価格の変動が激しく、投資した元本が損失するリスクもあるということを忘れてはいけません。
価格変動が小さく、比較的安定した資産の運用を目指すのであれば、債券や投資信託などへの投資を検討するといいでしょう。もちろん、これらの金融商品にも元本保証はありませんが、リスクを最小限に抑えることができるはずです。
3運用期間・目的で選ぶ
運用する目的や、いつまでに運用を終えたいのかを明確にして、その目標に合わせて資産運用の方法を選ぶのも大切です。
例えば、30代の人が資産運用をする場合、子供の養育費のための資産形成と老後のための資産形成をするのでは、資産を運用できる期間が大きく違うでしょう。
運用期間を長く確保し、投資期間を分散させることで比較的安定した資産運用が可能です。

1000万円・100万円・10万円金額別おすすめ資産運用法
ここからは、1000万円、100万円、10万円などの少額の、金額別のおすすめ資産運用方法についてご紹介します。
1000万円:投資信託と不動産投資がおすすめ

1,000万円以上の元手がある方におすすめの資産運用は、投資信託と不動産投資です。
投資信託の場合、プロが代わって運用してくれるため、専門的な知識はあまり必要ありません。最初に商品を選択すれば、あとはプロがお金を増やしてくれます。
不動産投資はマンションやアパートなどに投資して利益を得る方法。元手が1,000万円以上あるのであればぜひチャレンジしたい資産運用です。不動産投資では定期的な収入が見込めます。
100万円:つみたてNISA

100万円の元手で資産運用を始めたい方におすすめなのは「つみたてNISA」です。
つみたてNISAとは、2018年1月から始まった、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度。毎年40万円を上限として一定の投資信託を購入することができます。
購入した年から20年間、分配金と利益が課税されないため、非常にお得な制度です。厳選された商品の中から選ぶことができるので、初心者の方でも安心して運用することができるでしょう。
10万円などの少額:まずはネット預金から

元手が10万円などの少額の場合は、まずは元手を少しずつ増やしていきましょう。おすすめなのはネット銀行を活用することです。
近年大手メガバンクなどは低金利となっていますが、ネット銀行の場合は比較的金利が高いので、利用しない手はありません。
とはいえ、それではお金が増えるのに時間がかかると思う方もいるかもしれません。そんな方におすすめなのは、少額投資が可能なネット証券を利用する方法です。
たとえば、LINE証券であれば100円からの少額投資が可能です。元手が少額な場合は少しずつ投資していくことを心がけることでリスクを回避しやすくなるでしょう。
初心者必見!資産運用におすすめのネット証券6選

ここからは、選りすぐりのネット証券をご紹介します。なかでもおすすめなのは以下の3つです。
- ポイントプログラムが充実
- 楽天銀行などの他のグループと連帯でさらにお得に利用可能
- 業界最低水準の手数料※
- キャンペーンに参加でたくさんの特典を受けれる
楽天証券は、4年連続口座開設数で見事1位になった証券会社です。

| 取引手数料 | 【現物取引・超割コース】 ※1回の取引金額で取引手数料が決定
【いちにち定額コース】
|
|---|---|
| 取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) |
|
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン |
|
2SBI証券

- 売買手数料が安い
- 取扱い商品が多い
- 初心者でも安心な少額から投資OK
- 取引や投資信託でVポイントが貯まる・使える
- すぐ口座開設ができる
SBI証券は、ネット証券会社としてかなりの大手。口座開設数は業界トップクラスの910万を突破しています。
特に最大の特徴として、売買手数料の安さが挙げられます。
SBI証券の国内株式の現物取引「アクティブプラン」の場合、一日の取引合計額が50万円までなら売買手数料は無料。つまりタダで取引できてしまいます。
1日の取引合計額が50万円を超えると手数料が発生しますが、それでもかなり安め。

| 取引手数料 (税込) | 【国内株式現物取引・スタンダードプラン】 ※1注文の約定代金に対する手数料
【国内株式現物取引・アクティブプラン】
|
|---|---|
| 取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) |
|
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン |
|
3LINE証券

- 少額投資が可能(投資信託:100円、株式:数百円)
- 投資信託の手数料が無料
- 支払いにLINE Payが利用可能&LINEポイントも貯まる
- セキュリティがハイレベル
まず紹介する証券会社は、LINE証券です。
LINE証券は、LINEグループと野村証券グループがタッグを組んで始まったサービスで、スマホでの操作に特化しており初心者の方でも簡単に操作できます。
また、少額投資が可能なので、初心者の方にもぴったりです。
最低100円から投資できるので、気軽に資産運用をはじめられます。
引用元:投資信託 | LINE証券
| 取引手数料 (税込) | 【現物取引】※1注文の約定代金に対する手数料
※同一日に同一注文で複数の約定となった場合は、約定代金を合算し手数料を計算します。 |
|---|---|
| 取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) | – |
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン | – |
4マネックス証券

- 扱っている米国株の種類が豊富
- サポート体制が充実しているため初心者でも安心
- マネックスポイントを貯めて特典GETも可能

| 取引手数料 (税込) | 【現物取引・取引毎手数料コース】※1注文毎に手数料を計算
【一日定額手数料コース】
|
|---|---|
| 取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) |
|
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン |
|
5岡三オンライン証券

- 取引手数料が安い
- IPO取扱数が豊富
- 投資信託の購入時手数料が無料
取引手数料 | 【現物取引・ワンショット】 ※1注文の約定代金に対する手数料、インターネットでのお取引の場合
【現物取引・定額プラン】※1日の約定代金合計に対する手数料
|
|---|---|
取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) |
|
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン |
|
6松井証券

- アプリやツールの種類が豊富
- お得なキャンペーンが多い
- 顧客サポートが充実
松井証券の大きな特徴として、株式取引をする場合に約定金額が50万円以下であれば売買手数料が無料な点が挙げられます。

| 取引手数料 (税込) | 【現物取引】※1日の約定代金合計額
|
|---|---|
| 取扱商品 |
|
| 取引ツール(PC) |
|
| 取引ツール(スマホ・タブレット) |
|
| キャンペーン |
|
資産運用で失敗しないためには?

「資産運用に少し興味を持ったけれど、リスクが怖い」と考えている方も多くいらっしゃると思います。
そこで、今回は初心者でもできる失敗するリスクを抑えられる方法を紹介します。
※本記事の内容は、必ずリスクを抑えられる方法を紹介するものではありません。資産運用は自己の責任にて行っていただきますようお願いいたします。
1長期投資を選ぶ
長期投資は、1・2年と短い期間で投資をするのではなく10年〜20年といった長い間、預金や株・投資信託などの金融商品を保有し続ける投資方法のことです。
長期投資には、主に以下の2つのメリットがあります。
リスクを小さくできる

長期投資には、短期投資よりもリスクを小さくする効果が望めます。
金融商品の多くは常に価格が変動しているため、短期投資だとリスクが大きくなりがちです。
しかし金融商品を長く保有していれば、価格が下がってしまう時期があったとしてもまた再び上がることもあるため、リスクを軽減することが望めるのです。
複利効果を得られる
複利の場合には、元本+利子の合計金額に利子がつくため、投資期間が長くなればなるほど複利効果を期待できます。
例えば元本100万円を年率5%で運用すると、以下のように増えていきます。
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 |
|---|---|---|---|---|
| 105万円 | 110万2,500円 | 115万7,625円 | 121万5,506円 | 127万6,282円 |
5年後だと小さな差に感じますが、長期間で考えると大きな差を生みます。100万円が2倍の200万円になるのに、単利だと20年かかりますが、複利の場合15年で200万円になるのです。
このように複利効果があることが、長期投資をおすすめできるポイントのひとつです。
2分散投資をする

分散投資とは、複数の投資先に投資すること。投資先を1つに絞ってしまうと、投資対象の価値が下がったときに全ての資産がなくなってしまうリスクがあります。
そのリスクを減らすためにも、複数の投資先に投資することが重要です。また分散投資には、
- 資産の分散
- 地域の分散
- 時間の分散
の3種類があります。特に初心者の方には、分散投資がおすすめです。
3積立投資を選ぶ
積立投資は小額から始めることができるため、投資の雰囲気がわからない初心者の方に特におすすめな投資方法となっています。
また、ドルコスト平均法により平均購入価格を平準化させることができることも積立投資のメリットです。
資産運用初心者におすすめな本3選

ここでは、資産運用を始めようと思っている初心者が勉強するためにおすすめの本を3冊紹介します。
具体的な資産運用方法が書いてある本から、世界で100年読み継がれたお金の本質が書かれた漫画まで、資産運用初心者に知ってほしいことが書いてある本をまとめました。
本が苦手な方でも読みやすくわかりやすい形式の本を厳選して紹介していますので、気になった本がありましたらぜひ手に取ってみてください。
1図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!

「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!」は、山崎元さんと編集者である大橋弘祐さんの共著の本です。
実際に退職金500万円を手にした大橋弘祐さんが、定期預金以外でお金を増やすために、お金のプロである山崎元さんにどんな資産運用がおすすめなのかを聞いていく本です。
会話形式で読みやすく、具体的に「これはやらないほうがいい」「これだけはやったほうがいい」と教えてくれるので、そのまま真似をすることで失敗の少ない資産運用を始めることが可能です。
2本当の自由を手に入れる お金の大学

「本当の自由を手に入れる お金の大学」は、お金に関するノウハウをわかりやすく解説してくれるYouTuberの両さんが執筆した本です。
資産運用はもちろんのこと、それ以外の支出の減らし方や有益なお金の使い方など、お金に関する全てを広い視点でわかりやすく解説してくれます。
上記の「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!」を読んで、資産運用に関する具体的な方法を身につけた後、資産運用に回すお金を増やす目的で読むのがおすすめでしょう。
3漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 単行本

「バビロン大富豪の教えお金と幸せを生み出す五つの黄金法則」は、ジョージ・S・クレイソンさんが執筆、 坂野旭さんがイラスト、大橋弘祐さんが編集を担当した漫画本です。
漫画なので、短い時間ですらすら読める本です。古代バビロニアを舞台に、貧乏だった少年が大富豪になるために先人たちから教えを乞い、時に失敗しながら成長していく物語です。
目先のお金を得るテクニックではなく、お金に振り回されず、お金と長く付き合うためにどんな気持ちでいればいいのか、充実した人生を送るためのバイブルともいえる本でしょう。
資産運用に関するよくある質問
初心者の方には、ミドルリスク・ミドルリターンの資産運用がおすすめです。ミドルリスク・ミドルリターンであれば、投資した資産が一気に消えてしまうという心配がいりません。
【ミドルリスク・ミドルリターンの資産運用(例)】
・投資信託
・株式投資
・iDeCo(個人型確定拠出年金) など
初心者におすすめの証券会社はLINE証券です。LINE証券のおすすめポイントは主に3つです。
①投資信託の手数料が無料
②支払いにLINE Payが使える
③初心者でも安心な少額から投資OK
失敗のリスクを減らすためにできることは主に3つでしょう。
①長期投資を選ぶ
②分散投資
③積立投資
各証券会社の公式サイトで、シミュレーションが用意されている場合があります。SBI証券の公式サイトでは「積立シミュレーション」が利用できます。毎月の積立額や積立期間、利回り(年率)といった項目に入力するだけで、積立で将来いくらになるかを自動算出してもらえます。
大きなリターンを希望する場合には株式投資や投資信託がおすすめです。
資産運用おすすめのまとめ
今回の記事では初心者の方におすすめな資産運用を5つ紹介しました。特に投資信託は少額から投資をスタートできるので、初心者の方にもおすすめの資産運用です。
資産運用を行う上で気をつけたいのが、あくまでも中長期的な目線で利益を狙うこと。いきなり1,000万円など大きな利益を目指すのではなく、少しずつ利益をふくらませるのが重要です。
この記事を参考に、ぜひ資産運用デビューしてみてはいかがでしょうか。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。


